
Nobukazu Kuriki
栗城史多
登山家
“負け”もプロセス次第で“勝ち”になる
~エベレスト単独・無酸素登頂、Web生中継へ再挑戦~
2010年3月のFaust A.G.インタビューから半年〈当時の記事はコチラ〉。
栗城史多は満を持してエベレスト単独・無酸素登頂に向かった。
結論から言えば、それは「負け戦」だった。
だが、その「負け戦」に意味を持たせること、
そこにインターネットとソーシャルメディアを味方につけた栗城の、
冒険家としての矜持を見た。
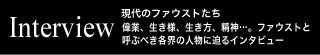

栗城史多
登山家
“負け”もプロセス次第で“勝ち”になる
~エベレスト単独・無酸素登頂、Web生中継へ再挑戦~
2010年3月のFaust A.G.インタビューから半年〈当時の記事はコチラ〉。
栗城史多は満を持してエベレスト単独・無酸素登頂に向かった。
結論から言えば、それは「負け戦」だった。
だが、その「負け戦」に意味を持たせること、
そこにインターネットとソーシャルメディアを味方につけた栗城の、
冒険家としての矜持を見た。
それは、とても不思議な体験だったと言わざるを得ない。2010年9月某日。目の前にあるPCのモニターに栗城のツイート(http://twitter.com/#!/kurikiyama/)が流れていた。
 2009年に続き、栗城が再度挑む世界最高峰エベレスト8848mの頂。
2009年に続き、栗城が再度挑む世界最高峰エベレスト8848mの頂。
 キャンプからTwitterで発信する栗城。
キャンプからTwitterで発信する栗城。
 ベースキャンプ(5300m)でシェルパら「栗城隊」と。
ベースキャンプ(5300m)でシェルパら「栗城隊」と。
「ナマステ。昨日無事に標高5300mのベースキャンプに入りました。そして先ほど、衛星とWi-Fiの基地建設終了。これでエベレストからつぶやけます! ここまで来るのに涙です。高山病に苦しみながらも基地を作ってくれた隊員に感謝です」
「ナマステ。今体調不良でなかなかつぶやけないです。ごめんなさい」
「高山病でカメラマン一名と副隊長が一旦下の村まで降りることになりました。僕も体調不良だけど、だけど、だけど、苦しみに感謝。やり遂げます」
そこにTwitterで栗城をフォローしている人々の会話が連なっていく。
東京からエベレストのあるカトマンズまで直線距離でもおよそ5500km超。その距離を超えて世界最高峰の山に立つ栗城の様子が伝わってくる。過酷さも、体調も、準備の様子も、そして栗城の決意も。
「これから登ります。単独・無酸素生中継です。いよいよです」
FacebookやTwitterに代表されるソーシャルネットワークは「共感のメディア」と呼ばれることがある。エベレスト挑戦中の栗城と、日本にいるわれわれの間の、およそ5500km以上の隔たりを感じるような、それでいて限りなく近いような感覚。5500km先にいるはずなのに目の前のモニタの50cm先にいるような感覚。それはさまざまな人の思いが、交錯している不思議なものだった。
「それが僕の狙いです。“冒険の共有”というもので。エベレストは(当然)行かないとわからない世界じゃないですか。もしくは、わかろうとしても山岳小説とか伝記や、下山後の記録映像しかないとか。ああいう情報をもっと身近に、しかも作り物じゃなくて明日どうなるかわからないみたいなリアリティを見せたかった」
ツイートはポジティブなことばかりではない。
8月17日、エベレスト遠征に向け日本を出発した栗城であったが、現地に行くまでに飛行機事故があり、栗城の仲間であるシェルパが一人亡くなっている。ニュースにもなった、ネパールのカトマンズからルクラへ向かうアグニエア航空の小型機墜落事故だ。栗城が乗る予定の一便前の飛行機だった。
「相当落ち込んだ」が、それでも現地からツイートする。
それが栗城の冒険のスタイルだからだ。
栗城がもっとも力を入れるのが現地からのインターネット中継だ。特に今回の中継は映像が非常に鮮明であり、「冒険の共有」を始めて数年間の集大成ともいえた。
栗城は撮影、中継、登山、日本でのマネジメントなど、仲間たちで「栗城隊」を結成する。かつて中継を始めた当初は、機材の山を見て「これで一体何をするつもりなのか。登山の邪魔になるだけでは」といぶかしがるシェルパもいたという。しかし何年も続けているうちに彼らの理解は深まっている。また、栗城隊の中には、日本のテレビ局から派遣されたスタッフもいた。挑戦をドキュメントとして撮影し、放送するためだ。
「その中に『なんだかよく分からないけれど連れてこられちゃいましたー』みたいな人がいて」
と栗城は楽しそうに話し始めた。聞けば、海外ロケさえも初めてという新しいスタッフだという。そんな彼が会社の命で派遣されたのが、いきなりエベレストという極地なのは、かなり酷な話だ。
「エベレストのベースキャンプに到着するまで、日本を出てから二ヶ月以上もかかるんですよ。そこでももちろん、高山病になったり、撮影の苦労があったり、いろいろあって…。衛星電話で家族と話をしたら、急に泣き始めちゃって」
それも無理はない。高い標高、薄い酸素、低温、食べるものも好きに食べられない。決まった人間と、ある種閉じられた世界に一カ月以上いるのだ。ところがそのエベレストの挑戦が終わり、帰ると決まった時に、なぜかまた彼が声を上げて泣いたという。極限状態に順応し、自分が全力を出して“生きている”と実感を得られる場所から帰るのがいやになったのだ。
「人は変われるんですよ。色白の人でしたが、日焼けして目もギラギラして。極地はやっぱり面白いですよね」
2010年9月、氷壁、クレバス、雪崩を乗り越え……そして下山を決意するその瞬間まで。
想像を絶する極地エベレストで格闘する栗城の生の姿をムービーで!
しかし、そんな極地への栗城の再挑戦は、これまで以上に自然との闘いだった。
「登頂にはあえて、あまり天気の良くない秋を選びました。ベストシーズンの春は登山家もいっぱいいるわけですし。僕は一人で登っていくということをやりたかったのです」
こうして入山したエベレストは、思いもよらぬ異常気象に見舞われた。エルニーニョ現象とラ・ニーニャ現象が同時に起こり、天気予報の専門家でも予測は困難を極める状況。荒天、豪雪である。天気予報とは基本的に過去のデータと経験則によるものだから、前例の無い天候では予測が困難になる。
前述の飛行機事故で、カトマンズで10日間足止めされ、エベレストでは5300mのベースキャンプを経て、C1と呼ばれる6400mのキャンプで4泊も閉じこめられた。冒険は当然ながら帰りの日にちまで設定し、それから逆算して予算、スタッフ、登頂スケジュール、食料などを決めていく。栗城はどんどん猶予がなくなっていくのを感じながら、ただ天候の回復を祈ってキャンプで待つしかなかった。
待機したまま9月の下旬、いよいよタイムリミットが迫ってきた。当初の計画から大きく遅れた影響で、この時期を過ぎると冬に入り、気圧が下がってくる。気圧が下がるとどうなるか? エベレストの山頂8848mは、酸素が薄いながらも前例もあり※、無酸素でたどり着くことができる。しかし、冬に気圧が下がると、酸素濃度が薄くなりすぎてしまい、無酸素登頂は不可能になる。もう間に合わない。天候はいっこうに回復しないが、ここで頂上へのアタックをかけるしかなかった
「すごくリスキーでした。野口さん(冒険家の野口健氏)にも『もっと身体を順応させるために時間をかけた方がいい』と言われたんですが。冬の気圧配置になったら完全にアウトなので……」
※前例として…史上初のエベレスト無酸素登頂は、1978年5月8日、ラインホルト・メスナーと、ペーター・ハーベラーのコンビによるもの。さらに、“単独”無酸素でのエベレスト登頂は、1980年8月21日、ラインホルト・メスナーが史上初めて達成した。
アタックを開始するも、状況が不利になっていたことは明らかだった。10月2日、7000m地点、ついに栗城は身体の負担を減らすため、背負っていた4kgある中継機材を下ろすことを決意。これはエベレスト登山の行程をインターネット生中継し、「冒険の共有」をするという夢を断念した瞬間でもあった。(ただし、この7000m地点で行った生中継は世界初の記録)
10/2、中継機材を下ろした7000m地点から栗城が行ったUSTREAM生中継【録画】!
それでも、まだ身体は完全には低酸素に順応していない。そしてついには気圧の低下が決定的となり、これ以上登っても山頂まで無酸素でたどり着くのは、理論的に不可能な状況になっていた。しかしそれは、頂上へのアタックを開始した時点で、ほぼわかっていた結果でもあったという。



 「試練に感謝」「生きていることに感謝」。栗城の口から発せられる言葉は常に生への感謝に充ちていた。
「試練に感謝」「生きていることに感謝」。栗城の口から発せられる言葉は常に生への感謝に充ちていた。
率直に言えば、「負け戦」確定だった。
登山家は山に登るのが使命であり、存在価値でもある。ところが目標である頂上に行くことは、始めからほぼ不可能と分かっていた。そんな負け戦を選ぶ心境はどのようなものだろう。
「一人スタッフも亡くなっているし、ここまで頑張って来られたんだというところを彼にも皆さんにも見せたかったんです」と栗城は飾ることなく語った。
「例え頂上は無理でも、行けるところまで行きたいと。気圧の低下は決定的でしたが、それでも何が起きるかわからないのが山ではありますし。なおかつ、ちゃんと自分で帰ってこられる地点を探そうと。そして7000mを超えて行ったんですが、もう自分の左右が雪崩れちゃってて、これは危険だと自覚しました。紫外線に目をやられちゃっているし、視界は悪いしで、状況を俯瞰して見ることはできませんでしたが、足元の雪質からして、あれ以上は進めませんでした」
どこかで引かねば死ぬ。しかし、引くに引きたくない。山の女神に後ろ髪を引かれつつ、栗城は足を止め、皆の元に引き返すことになる。
「引くに引けない…という葛藤は多分冒険家なら皆同じだと思うのですけど…」
そこは標高約7750mの地点だった(2010年の最高到達地点を記録)。もちろん頂上に行きたかったが、仕方ないと栗城は言う。
「頂上というのは結果なんですけど、一番のゴールはその中でいかに自分が成長するかという過程なんです。そのためにあるのが登山であり、山頂へのチャレンジなのではと思っています。だから、プロセスのために挑戦したといってもいいかもしれません」
こうして栗城の挑戦は終わりを迎えた。
エベレストに挑む栗城と約5500km離れた日本でモニターの前にいる我々と、共感がピークに達したのは、その時だったように思う。リアルとネットの存在感がないまぜになったような、不思議な空間だった。
それまでTwitter上では栗城に対して、「がんばってください」「応援しています」「頂上に行けるといいですね」という、至極まっとうで、誤解を恐れずに言えば、どこか他人ごとが前提であるようなコメントが並んでいたのに、その時は「自分は本当は●●をやりたかったんですが、やっぱりこれからチャレンジしてみます」「栗城さんが頑張っているので僕も●●を始めます」と、挑戦や目標を共有したり、自ら行動を起こそうとする内容に変化していた。
栗城のチャレンジと自分のチャレンジを重ね合わせるように、ネットで繋がった人々の言動が変わっていったのだ。
栗城の冒険の意義は、ここに現れている。成功か否かの二極ではなく、挑戦することと、そのプロセスに価値があるということを、行動で伝えていく。これまでの登山家は成功して始めてニュースになり、失敗すれば話題にも上らなかった。成功しなければ、彼らの伝えたいことも伝わらなかったわけだ。
ところが栗城は、インターネット中継とソーシャルネットワークの活用によって、結果以前のプロセスをさらけ出すことで、プロセスの価値を広く伝え、「挑戦すること」について、皆が共に考える触媒のような役割を、冒険に加えることができた。
「登山家って、弱音を吐いちゃいけないとか、強くあらねばならないとか、どうしてもそう思われがちなんです」
と栗城は前置きしてから、一気に話し始めた。
僕は結構、山で泣いちゃったり、裏側の辛いところとかカッコ悪いところを出しちゃったりするんですよね。やっぱり人間は本来弱い生き物だと思うんです。でも弱いからこそ、頑張ったり、成長したりするのではないかと。だから、僕はそういうところをさらけだしたいと思っています。悔しかったら悔しがるし、泣いて弱音を吐いてもいいんですよ。それからまた頑張ればいいと思いませんか」
これまで「共感」とは、本を読んだり実際に講演を聞いたりと、限られた数の人々が得られるものだった。今はネットとソーシャルメディアによって、即時に多数の人々に共感が伝わる。
栗城にとって、そして彼の挑戦を見た人々にとって、得られたものがそれぞれにあっただろう。今回のエベレスト登頂は「共感の登山」として、必ずしも負け戦ではないのだ。
エベレストからの下山途中、栗城はこうツイートしている。
「栗城です。ベースキャンプに着きました。生きていることに感謝。試練に感謝。支えてくれてこの冒険を共有できた人達に感謝。そして僕は諦めません」
次のチャレンジは、来年2011年春、ヒマラヤの8000m峰。そして秋には、三度目のエベレストに勝ちに行く。
帰国直後、成田空港での栗城をインタビュー【ムービー】
オフィシャルサイト
http://kurikiyama.jp/
YouTubeオフィシャルチャンネル
http://www.youtube.com/user/kurikiyama

登山家
くりき・のぶかず。1982年生まれ。登山家。大学時代から登山を始め、2年後にマッキンリー単独登頂に成功。2005年、南米最高峰アコンカグアに単独登頂。2007年に世界第6位の高峰チョ・オユー登頂時から動画配信を行う。2008年、マナスルで日本人初の単独・無酸素登頂と山頂からのスキー滑降に成功。2009年ダウラギリからインターネットライブ中継を行う。10月、エベレスト単独・無酸素登頂に挑むも、8000m付近で断念。2010年10月、エベレストに再挑戦するも約7750m付近で断念。2011年秋、エベレスト登頂の瞬間のインターネット生中継を計画中。
Text : Toru Mori(tsunagaru Inc.)
2010/12/16




















































地球最高の冒険者〈ファウスト〉たちを讃えよ! サイバードグループ・プレゼンツ「ファウストA.G.アワード 2015」開催概要
バトンが紡いだ未知なる40キロへの挑戦 中川有司 株式会社ユニオンゲートグループ 代表取締役&グループCEO / 株式会社セルツリミテッド 代表取締役
「至上の瞬間は、あらゆる時に訪れる」 G.H.MUMMの静かなる挑戦 ディディエ・マリオッティ G.H.マム セラーマスター
ネクタイを外したときに試される 男のカジュアルスタイルの極意とは ファウストラウンジ第10弾 「男の嗜み 〜ファウスト的 スタイリングの極意〜」