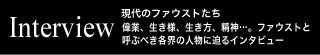Dai Tamesue
為末 大
プロハードラー
貢献の意思がアスリートを強くする
サムライ・ハードラーとも呼ばれる日本を代表するスプリンター。一流アスリートであるとともに、競技の世界を飛び越えた発想と着眼、人脈でも知られる異彩の彼は、3・11の東日本大震災後、その日ごろの活力をいち早く転嫁し、数多くのトップアスリートたちに呼びかけ、義援金を募る活動を展開した。彼が「ジャストギビング」にて結成したTEAM JAPANが募った義援金は3200万円を上回る(2011年10月現在)。アスリートたちが持つ社会へのメッセージ性と社会貢献とをみごとに結び付けた、その研ぎ澄まされた思考に迫る。